 |
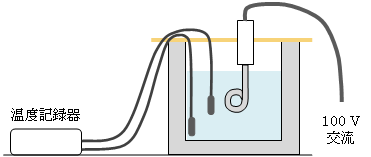 |
電熱線(ヒータ)で水を加熱し,一定時間ごとに水温を測る実験の例を示す。
ヒータは,旅行用の小型の投げ込みヒータを使った。
100V用300Wと表記されているが,実験時には実際に電圧と電流を測ってワット数を求める。
容器は,発泡スチロールとビーカーを使用し,水の量は300 ccとした。
水温は,2つのサーミスタを持つ温度記録器をで計測した。
300 ccの水(室温17 ℃)に投げ込みヒータと温度センサを2つ入れる。
発泡スチロールの容器は蓋なしであり,容器の上部に割り箸を渡してこれにヒータやセンサを固定する。
ヒータは計測開始前に別な水中で1分ほど通電しておき,開始時刻に発泡スチロールの容器にすばやく移す。その後30秒毎に2つの温度センサの温度を読む。
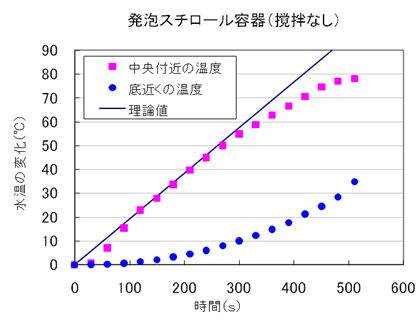
計測中に水を攪拌しないと,グラフのように底付近の水温はなかなか変わらない。
この実験では,必ず水を攪拌しながら測定しなければならないことがわかる。
このグラフの理論値は,以下のようにして描いたものである。
実験中のヒータの電圧 105 Vと電流 2.68 A から電力 281.4 W となり,このヒータは1秒間に 281.4/4.186 = 67.2
cal の熱を出すことがわかる。
したがって,300 ccの水の温度上昇は,67.2/300 = 0.19 ℃/s となる。
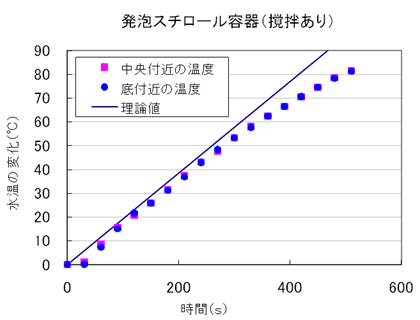
実験法は上と同じだが,計測中に水を軽く攪拌する。
室温や電圧・電流も上とはわずかに異なる。
計測中に水を軽く攪拌すれば,2つのセンサの温度はほとんど等しくなる。
グラフから,温度上昇が小さい間は,理論とよく一致することがわかる。
高温になると,水や容器の表面から逃げる熱が大きくなる。
特に,気化熱は大きな効果を及ぼす。そのため,これらを無視した理論からはずれてくる。
※これらの実験は沸点近くまで計測しているので,この後水温はほぼ横ばいになる。
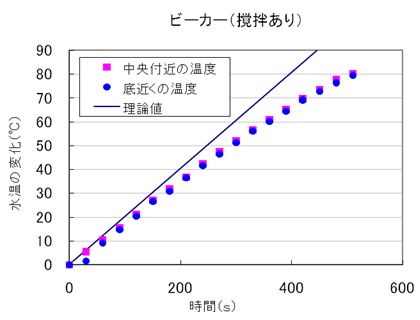
同じ実験を,容器をビーカーに代えて行ってみた。
結果は予想される通りで,発泡スチロールの容器と比べると,低温時でも放熱が大きく,温度が上がりにくいことがわかる。
グラフでは,意外に理論に近いように見えるが,やはり発泡スチロールの容器で実験する方がよい。
投げ込みヒータと発泡スチロールの容器を使うと,簡単にジュール熱の実験ができる。
水温が60〜70℃以下なら気化熱の影響はさほど大きくないので,実験はこの範囲で行えばよい。